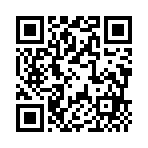スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2ヶ月以上たった、被災地の今(2)
2011年05月30日
つづき…。

↑下の階は鉄骨のみが残り、奥の景色が透けて見える。

↑海岸沿いの道は寸断され、公衆トイレ?も傾いている。

↑がれきの様子から、赤いラインまで津波が到達した様子。

↑くしゃっと潰れた家も、未だそのまま。

↑窓ガラスはすべて無く、最上階の窓の奥にはがれきが…。
屋内を津波が渦巻く様子が想像できる。

↑ポツン、ポツンとある建物も、残っているのはカタチだけ。

↑津波で流された網が、
4階以上もある建物をすっぽり覆い、
そのままの状態で建っていました。

↑どこからどこまでが、道路や家だったのでしょうか。
かろうじて歩道らしき道が確認できるくらい。

↑海から離れた場所でも
砂浜の砂がたくさん流れ着いていました。
いったいどれくらいの距離を流れてきたのでしょう。

↑今回の大災害によって、地形も変わってしまったそう。

↑地震と津波のダブルの被害の大きさを物語っています。
※写真は、宮城県の気仙沼市、南三陸町あたり。
地元の方が、
「この津波で、地形も変わってしまった…」と
ポツンとつぶやいてみえました。
以前の状態を知らない私にでも、
意味がわかりました。
どこが川で、どこからが海で、
どのあたりまで家があったのか…。
そのほんの数十分の時間で、
すべてが変わったのだと。
この先、長い年月をかけて復興した後でも、
この悲劇が風化することなく、
しっかりと記憶し、策を施し、
未来へつなげていかなければ。
〜 つみきレターSTAFF 〜

↑下の階は鉄骨のみが残り、奥の景色が透けて見える。

↑海岸沿いの道は寸断され、公衆トイレ?も傾いている。

↑がれきの様子から、赤いラインまで津波が到達した様子。

↑くしゃっと潰れた家も、未だそのまま。

↑窓ガラスはすべて無く、最上階の窓の奥にはがれきが…。
屋内を津波が渦巻く様子が想像できる。

↑ポツン、ポツンとある建物も、残っているのはカタチだけ。

↑津波で流された網が、
4階以上もある建物をすっぽり覆い、
そのままの状態で建っていました。

↑どこからどこまでが、道路や家だったのでしょうか。
かろうじて歩道らしき道が確認できるくらい。

↑海から離れた場所でも
砂浜の砂がたくさん流れ着いていました。
いったいどれくらいの距離を流れてきたのでしょう。

↑今回の大災害によって、地形も変わってしまったそう。

↑地震と津波のダブルの被害の大きさを物語っています。
※写真は、宮城県の気仙沼市、南三陸町あたり。
地元の方が、
「この津波で、地形も変わってしまった…」と
ポツンとつぶやいてみえました。
以前の状態を知らない私にでも、
意味がわかりました。
どこが川で、どこからが海で、
どのあたりまで家があったのか…。
そのほんの数十分の時間で、
すべてが変わったのだと。
この先、長い年月をかけて復興した後でも、
この悲劇が風化することなく、
しっかりと記憶し、策を施し、
未来へつなげていかなければ。
〜 つみきレターSTAFF 〜
2ヶ月以上たった、被災地の今
2011年05月29日
〜そこにあった暮らしは、今はまだない 〜
わたしが被災地に着いたのは、5月19日の明け方。
2ヶ月たったとは思えない光景が広がっていました。
これでも被災当初よりは、
格段に片付いたのだそうです。
確かに、地震直後のTVや新聞、
その他の媒体に掲載された写真と比べてみると、
断然ガレキが減っているのも、
大分水が引いたのもわかりました。
それでも、実際に初めて目にした私には、
とてつもない事が起きた場所だということが、
説明なくてもわかるほどの状態でした。
いきなりあらわれたその光景を前に、
ただ呆然と…。
「すごい…」の声しか出ませんでした。
ただ手を合わせ祈ることしかできませんでした。
この状況をあえてお伝えすることで、
風化してしまわないよう、
長い長い復興までの道のりを
長期的に支援していかなければならないことを、
より多くの人に知ってほしいと思います。
この度の震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると共に、
被災地、被災者の皆様にそのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。
※画像はクリックすると大きな画像でご覧いただけます。

↑流れ着いたであろう車もそのまま。

↑ガソリンスタンドだったのでしょうか。

↑山からも海からも距離のある田んぼに流木が。

↑高さのある自動車道の上に、
屋根だけが取り残されていました。

↑ひと繋ぎだったであろう、
津波で削りとられた奥の森林。

↑あたり一面、人が暮らしていた気配は消え去りました。

↑壊れた橋を修復中。
道路にはまだガレキが。

↑垂れ下がった電線。
この1本の電線が途絶えるだけでも、
いったいどれだけの影響があったことでしょう。
奥にはポツンとたたずむ建物。

↑やじるしのところが堤防。
堤防の陸側も川のようになってしまった。

↑山と津波による荒れ地の、奇妙なコントラスト。何もない。

↑ほんの少しの高低差で、ぽつんと残った家も。
※写真は、宮城県の気仙沼市、南三陸町あたり。
〜 つみきレターSTAFF 〜
わたしが被災地に着いたのは、5月19日の明け方。
2ヶ月たったとは思えない光景が広がっていました。
これでも被災当初よりは、
格段に片付いたのだそうです。
確かに、地震直後のTVや新聞、
その他の媒体に掲載された写真と比べてみると、
断然ガレキが減っているのも、
大分水が引いたのもわかりました。
それでも、実際に初めて目にした私には、
とてつもない事が起きた場所だということが、
説明なくてもわかるほどの状態でした。
いきなりあらわれたその光景を前に、
ただ呆然と…。
「すごい…」の声しか出ませんでした。
ただ手を合わせ祈ることしかできませんでした。
この状況をあえてお伝えすることで、
風化してしまわないよう、
長い長い復興までの道のりを
長期的に支援していかなければならないことを、
より多くの人に知ってほしいと思います。
この度の震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると共に、
被災地、被災者の皆様にそのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。
※画像はクリックすると大きな画像でご覧いただけます。

↑流れ着いたであろう車もそのまま。

↑ガソリンスタンドだったのでしょうか。

↑山からも海からも距離のある田んぼに流木が。

↑高さのある自動車道の上に、
屋根だけが取り残されていました。

↑ひと繋ぎだったであろう、
津波で削りとられた奥の森林。

↑あたり一面、人が暮らしていた気配は消え去りました。

↑壊れた橋を修復中。
道路にはまだガレキが。

↑垂れ下がった電線。
この1本の電線が途絶えるだけでも、
いったいどれだけの影響があったことでしょう。
奥にはポツンとたたずむ建物。

↑やじるしのところが堤防。
堤防の陸側も川のようになってしまった。

↑山と津波による荒れ地の、奇妙なコントラスト。何もない。

↑ほんの少しの高低差で、ぽつんと残った家も。
※写真は、宮城県の気仙沼市、南三陸町あたり。
〜 つみきレターSTAFF 〜
被災地の状況
2011年05月28日
今回、被災地に行ってみてわかった、
テレビや新聞では報じられていない現実がありました。
今回訪れた避難所から
たった2km先の避難所には、
おかわりができるくらいの食料があり、
ボランティアセンターが併設となっている、
今回の避難所までは届かず少なかったという、
支援物資による避難所の格差というのを
まのあたりにしました。
遠くに住むわたしたちは、
情報がないため、報道にたよるしかありません。
そうして報道された所には、
大量の物資や支援があつまり、
そうでない所との差が生まれてしまうのです。
報道できないくらい被災した場所、
立ち入り出来ない場所こそ、
孤立していたり、
交通手段が失われた、
一番悲惨な状況なのだろうと思います。
そういう所には、
短期の滞在ではなく、長期的に滞在し、
足を使って情報を得るしかありません。
どうしても格差ができてしまうかもしれませんが、
これを暖和できる策を
考えておかなければならないのだと感じました。
今回、被災地の写真を撮るか撮らないかで
自分の中で葛藤がありました。
撮っていいものなんだろうか…。。。
当事者ではないわたしが写真を撮ること。
それは許されるのだろうか?
今回の大震災はたくさんの人の不幸があります。
被災地にカメラを向けるたび、
何か悪い事をしているような気がして…。
でも、被災地から遠くに住むわたしたち、
日本中のみんなが、
今回の震災を通して学ばなければならないんだと思いました。
わたしは、カメラをむけ、撮影したあと、
各所に手を合わせ、
心の中でご冥福を祈りました。
そして、
この震災を無駄にはしない。
そう自分に何度も何度も語りかけました。
だけど、それでも撮れないものがありました。
「OK」と書かれたボート。
これは、捜索済みというしるしだそうです。
そこにはもしかしたら被災した方の
遺体があったかもしれません。
「支援ありがとうございます」という、
ベニア板にスプレーで書かれた看板。
被災地のどなたかが、
現地まで足を運んだ様々な方に向けて
書いてくださったのでしょう。
報道にはない、
実際に訪れた人にしか伝わらないこと。
目に見えない何かがそこにありました。
避難所の格差。
報道のカメラマンたちの葛藤。
様々なオモイやキモチが
今回被災地に訪れたことで感じました。
日本中、いや、世界中、
どこにいても、
いつ、何が起こるかなんてわかりません。
何も起こらない確立なんて、
どこにいてもゼロではないのです。
わたしたちの住む飛騨でも、
万が一の場合を想定して、
しっかりと対策をねること、
そしてそれを全員で共有すること、
それを継続していくこと、
が必要だと思いました。
まずは、今回各幼稚園や保育所で学んだ、
「月イチの真剣な避難訓練」が、
なんとか実施できないかと思っています。
もしかしたら、もう行われているかもしれませんが、
私の小さい頃の記憶では、
年に何回かあったくらいの記憶しかありません。
もし、行政機関に勤めてみえる方や、
保育園や学校に勤めてみえる方が
このブログを見ていただいているなら、
是非提案していただきたいのです。
また、もしもの時の避難場所の把握。
これは、だれでも少し調べればできると思います。
大切な人たちや家族を守るため、
家族会議をしたり、
情報を調べたりして、
個々でも危機管理が必要だと思いました。
守れる命を守るために。
〜 つみきレターSTAFF 〜
テレビや新聞では報じられていない現実がありました。
今回訪れた避難所から
たった2km先の避難所には、
おかわりができるくらいの食料があり、
ボランティアセンターが併設となっている、
今回の避難所までは届かず少なかったという、
支援物資による避難所の格差というのを
まのあたりにしました。
遠くに住むわたしたちは、
情報がないため、報道にたよるしかありません。
そうして報道された所には、
大量の物資や支援があつまり、
そうでない所との差が生まれてしまうのです。
報道できないくらい被災した場所、
立ち入り出来ない場所こそ、
孤立していたり、
交通手段が失われた、
一番悲惨な状況なのだろうと思います。
そういう所には、
短期の滞在ではなく、長期的に滞在し、
足を使って情報を得るしかありません。
どうしても格差ができてしまうかもしれませんが、
これを暖和できる策を
考えておかなければならないのだと感じました。
今回、被災地の写真を撮るか撮らないかで
自分の中で葛藤がありました。
撮っていいものなんだろうか…。。。
当事者ではないわたしが写真を撮ること。
それは許されるのだろうか?
今回の大震災はたくさんの人の不幸があります。
被災地にカメラを向けるたび、
何か悪い事をしているような気がして…。
でも、被災地から遠くに住むわたしたち、
日本中のみんなが、
今回の震災を通して学ばなければならないんだと思いました。
わたしは、カメラをむけ、撮影したあと、
各所に手を合わせ、
心の中でご冥福を祈りました。
そして、
この震災を無駄にはしない。
そう自分に何度も何度も語りかけました。
だけど、それでも撮れないものがありました。
「OK」と書かれたボート。
これは、捜索済みというしるしだそうです。
そこにはもしかしたら被災した方の
遺体があったかもしれません。
「支援ありがとうございます」という、
ベニア板にスプレーで書かれた看板。
被災地のどなたかが、
現地まで足を運んだ様々な方に向けて
書いてくださったのでしょう。
報道にはない、
実際に訪れた人にしか伝わらないこと。
目に見えない何かがそこにありました。
避難所の格差。
報道のカメラマンたちの葛藤。
様々なオモイやキモチが
今回被災地に訪れたことで感じました。
日本中、いや、世界中、
どこにいても、
いつ、何が起こるかなんてわかりません。
何も起こらない確立なんて、
どこにいてもゼロではないのです。
わたしたちの住む飛騨でも、
万が一の場合を想定して、
しっかりと対策をねること、
そしてそれを全員で共有すること、
それを継続していくこと、
が必要だと思いました。
まずは、今回各幼稚園や保育所で学んだ、
「月イチの真剣な避難訓練」が、
なんとか実施できないかと思っています。
もしかしたら、もう行われているかもしれませんが、
私の小さい頃の記憶では、
年に何回かあったくらいの記憶しかありません。
もし、行政機関に勤めてみえる方や、
保育園や学校に勤めてみえる方が
このブログを見ていただいているなら、
是非提案していただきたいのです。
また、もしもの時の避難場所の把握。
これは、だれでも少し調べればできると思います。
大切な人たちや家族を守るため、
家族会議をしたり、
情報を調べたりして、
個々でも危機管理が必要だと思いました。
守れる命を守るために。
〜 つみきレターSTAFF 〜