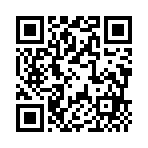スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
イベント風景
2011年04月26日
世界生活文化センターで開催された、
「アースデー飛騨高山2011」の会場にて、
「つみきレター」のメッセージ募集をした時の様子です!
★1日目
コンベンションホール奥のブースをお借りしました!


お子様連れのママさんが
ゆっくりメッセージを考えられるように、
「らくがきテーブル」を用意しました♪
みんなのらくがき作品です!

★2日目
2日目は、場所を移動!!
コンベンションホール入り口にて。
小さいこどもたちから、大人まで、
たくさんの方がメッセージを書いてくださいました!
ありがとうございました!

この2日間でのメッセージ数は、63通!
飛騨のみなさんのオモイ、
しかと受け取りました!
このメッセージを、
これから出来てくる「つみき」に
ひとつひとつ心を込めて書き込んでいきます!
〜つみきレターSTAFFより〜
「アースデー飛騨高山2011」の会場にて、
「つみきレター」のメッセージ募集をした時の様子です!
★1日目
コンベンションホール奥のブースをお借りしました!


お子様連れのママさんが
ゆっくりメッセージを考えられるように、
「らくがきテーブル」を用意しました♪
みんなのらくがき作品です!

★2日目
2日目は、場所を移動!!
コンベンションホール入り口にて。
小さいこどもたちから、大人まで、
たくさんの方がメッセージを書いてくださいました!
ありがとうございました!

この2日間でのメッセージ数は、63通!
飛騨のみなさんのオモイ、
しかと受け取りました!
このメッセージを、
これから出来てくる「つみき」に
ひとつひとつ心を込めて書き込んでいきます!
〜つみきレターSTAFFより〜
「つみきレター」はじまりました!
2011年04月25日
4月23日、24日に、
世界生活文化センターで開催された、
「アースデー飛騨高山2011」の会場にて、
「つみきレター」のメッセージ募集をいたしました!
ご参加くださった飛騨のみなさま、
本当にありがとうございました!
飛騨のみなさんのメッセージは、
2日間で、63名集まりました!
これから、
ご協力くださる
「seedsさん」
「田中建築さん」
「工匠 金村さん」
「(有)永山建築さん」と一緒に、
つみき作りがはじまります!
随時「ママ友のチカラ募金」サイトやこのブログにて
経過をお知らせしていきますので、
ぜひチェックお願いします!
「つみきレター」のイキサツとオモイは
コチラから↓
http://www.sparkingholiday.com/mama/tsumiki.html
まずは、アースデーでメッセージを書いてくださった
飛騨のみなさまへのお礼まで。
本当にありがとうございました!
追伸:
ママ友のチカラ募金サイトでの
メッセージ募集も近々開始しますので、
もう少しお待ちくださいませ★
〜つみきレターSTAFFより〜
世界生活文化センターで開催された、
「アースデー飛騨高山2011」の会場にて、
「つみきレター」のメッセージ募集をいたしました!
ご参加くださった飛騨のみなさま、
本当にありがとうございました!
飛騨のみなさんのメッセージは、
2日間で、63名集まりました!
これから、
ご協力くださる
「seedsさん」
「田中建築さん」
「工匠 金村さん」
「(有)永山建築さん」と一緒に、
つみき作りがはじまります!
随時「ママ友のチカラ募金」サイトやこのブログにて
経過をお知らせしていきますので、
ぜひチェックお願いします!
「つみきレター」のイキサツとオモイは
コチラから↓
http://www.sparkingholiday.com/mama/tsumiki.html
まずは、アースデーでメッセージを書いてくださった
飛騨のみなさまへのお礼まで。
本当にありがとうございました!
追伸:
ママ友のチカラ募金サイトでの
メッセージ募集も近々開始しますので、
もう少しお待ちくださいませ★
〜つみきレターSTAFFより〜
今日の新聞ピックアップ☆全国の学校耐震化
2011年04月17日
今回の東日本大震災を受け、
全国の学校耐震化(400億円)が盛り込まれました。
対象が全国なので、
飛騨も例外ではないということでしょう。
私の母校である古川西小学校も、
安全・安心な学校づくり交付金事業の一環で、
耐震と大規模が行われ、ほぼ完了しました。
※参考資料↓
http://www.city.hida.gifu.jp/gyousei/g_oshirase/2011/0311.../taisin_2011.pdf
みなさんのお子さんが通っている学校の
耐震具合はご存知ですか?
この機会に知っておくことも必要なのではないでしょうか?
ちなみに、上記の参考資料は、
「古川西小学校 耐震」とグーグルで検索したら出てきました。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
政府、民主党は16日、東日本大震災の復旧・復興にむけた2011年度第1次補正予算案に関し、全国の学校耐震化経費400億円を新たに盛り込む方針を固めた。野党に配慮した修正で、早期成立へ協力を促す狙い。18日の民主党と自民、公明両党の政策責任者協議で提示する。
また、与野党双方に慎重論があった政府開発援助(ODA)の1千億円の削減幅も500億円に圧縮。これまで7万戸分としていた被災地の仮設住宅建設費は10万戸分に拡大する。
いずれの修正に関しても国債の追加発行などはせず1兆数千億円で調整していた公共時事業費を削減することで帳尻を合わせる考え。
4兆円規模の全体額は維持する。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

全国の学校耐震化(400億円)が盛り込まれました。
対象が全国なので、
飛騨も例外ではないということでしょう。
私の母校である古川西小学校も、
安全・安心な学校づくり交付金事業の一環で、
耐震と大規模が行われ、ほぼ完了しました。
※参考資料↓
http://www.city.hida.gifu.jp/gyousei/g_oshirase/2011/0311.../taisin_2011.pdf
みなさんのお子さんが通っている学校の
耐震具合はご存知ですか?
この機会に知っておくことも必要なのではないでしょうか?
ちなみに、上記の参考資料は、
「古川西小学校 耐震」とグーグルで検索したら出てきました。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
政府、民主党は16日、東日本大震災の復旧・復興にむけた2011年度第1次補正予算案に関し、全国の学校耐震化経費400億円を新たに盛り込む方針を固めた。野党に配慮した修正で、早期成立へ協力を促す狙い。18日の民主党と自民、公明両党の政策責任者協議で提示する。
また、与野党双方に慎重論があった政府開発援助(ODA)の1千億円の削減幅も500億円に圧縮。これまで7万戸分としていた被災地の仮設住宅建設費は10万戸分に拡大する。
いずれの修正に関しても国債の追加発行などはせず1兆数千億円で調整していた公共時事業費を削減することで帳尻を合わせる考え。
4兆円規模の全体額は維持する。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

今日の新聞ピックアップ☆災害時 炊き出しマニュアル
2011年04月17日
現在、様々なボランティア団体によって、
被災地では炊き出しが行われています。
この「炊き出しマニュアル」というのは、
2004年の中越地震から始まり、
能登半島地震や新潟中越沖地震の時にも出動したそう。
※2008年の岩手・宮城内陸地震では、募集がなかったため出動なし。
私は、そのようなマニュアルがあることを
初めて知りました。
記事によると、
このメニューは「災害時 炊き出し」という名にふさわしく、
様々な面からみてあり、メニュー以外のゴミ処理や場所、排水にいたるまで、
実に細かく想定され、マニュアル化されているそうです。
そうなると…
どんなものなのだろう?
実際にみてみたい!と思い、
マニュアルを検索してみましたが、
見つからず。。。
特定非営利活動法人 キャンパー
http://www.camper.ne.jp/npo/
というところが発行しているらしく、
見てみるけれども見当たらない。。。
「災害時炊き出しマニュアル2009-10企業版」
というものも発行されているみたいだけど、
やっぱり見つからない。。。
日本調理科学会のHPにもない。。。
いったいどこに!?
とりあえず、新潟バージョンを見付けたので
リンクしておきます。
御参考までに。
eiyou-niigata.jp/pdf/saigaijisien_nagaoka.pdf
本当に細かくマニュアル化されています。
子どもの頃に地元の子ども会で行ったキャンプの
「キャンプのしおり」を思い出しました。
こうしてあらかじめマニュアル化しておけば、
いざという時に、ドタバタしなくてすむんだなと思いました。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
未曾有の東日本大震災は莫大な被害を及ぼし、知り合いの大学の先生も被災し、復旧活動とともに、年度末であったことから入学試験、就職、卒業式、学生の安否確認、大学施設の管理、授業再開に向けての対応をされている。もちろんこれだけではないので、空を見て天気を気にする余裕もない時もあるとのこと。
被害者の方々は私の想像を絶する生活をされておられるのである。
このような生活の中でも、私の専門が食の分野であるためか、メールで食生活について時々触れられている。「知り合いの方からいただいた綜合ビタミン剤を飲みました」「温かい蕎麦を振る舞ってもらいました」「カップ麺のつゆを処理する方法を考えました」などを見るにつけて、私で支援できることはないかといつも思う。
多くの人も同様に何か手伝いたいという思いで行動を起こしておられることであろう。しかし、現地に行って被災者の方々を支援するとなると「思い」からのスタートはするのであるが「思い」だけでは困難に遭遇することも多々あるのではないだろうか。
日本調理科学会では、災害救援の他に、大量調理システムの研究開発及び普及促進、地域防災力向上、ネットワーク県境細微などを活動事業としているNPOと一緒に「災害時の炊き出しメニュープロジェクト」を2005年に立ち上げ、「災害時 炊き出しマニュアル」の発行を毎年行ってきている。
このNPOは2004年の中越地震の炊き出しから始まり、能登半島地震、新潟中越沖地震の災害に出動したという経験をもつ団体である。
2008年の岩手・宮城内陸地震では、外部ボランティアの募集がなかったため、出動ができなかったそうである。
メニュー作成にあたってはNPOの出動経験と学会が蓄積している専門知識とで、心理面、調理面、衛生面、栄養面、地方の特色を活かした料理、アレルギー除去食、高齢者用軟食への対応、冷凍食材の利用、食の安全などと毎年テーマを決めて取り組み、朝昼夕の2食・2週間分のメニューをそれぞれの支部で作成した。1食について下準備・調理作業時間を2時間以内に収まるようにし、タイムチャートも合わせて作成している。
メニューだけでなく、炊き出しにあたっての使用機材、炊き出し場所、水、排水、電気、ゴミ処理、食材、食器、現地までの道路状況、駐車・宿泊場所など、すべてマニュアル化されている。このような経験と知識の積み重ねがあってこそ、被災者の方への有効な支援が可能になってくる。このNPOからは、マニュアルの成果を踏まえ、3月19日から活動を継続しておられるとの連絡が入ってきている。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

被災地では炊き出しが行われています。
この「炊き出しマニュアル」というのは、
2004年の中越地震から始まり、
能登半島地震や新潟中越沖地震の時にも出動したそう。
※2008年の岩手・宮城内陸地震では、募集がなかったため出動なし。
私は、そのようなマニュアルがあることを
初めて知りました。
記事によると、
このメニューは「災害時 炊き出し」という名にふさわしく、
様々な面からみてあり、メニュー以外のゴミ処理や場所、排水にいたるまで、
実に細かく想定され、マニュアル化されているそうです。
そうなると…
どんなものなのだろう?
実際にみてみたい!と思い、
マニュアルを検索してみましたが、
見つからず。。。
特定非営利活動法人 キャンパー
http://www.camper.ne.jp/npo/
というところが発行しているらしく、
見てみるけれども見当たらない。。。
「災害時炊き出しマニュアル2009-10企業版」
というものも発行されているみたいだけど、
やっぱり見つからない。。。
日本調理科学会のHPにもない。。。
いったいどこに!?
とりあえず、新潟バージョンを見付けたので
リンクしておきます。
御参考までに。
eiyou-niigata.jp/pdf/saigaijisien_nagaoka.pdf
本当に細かくマニュアル化されています。
子どもの頃に地元の子ども会で行ったキャンプの
「キャンプのしおり」を思い出しました。
こうしてあらかじめマニュアル化しておけば、
いざという時に、ドタバタしなくてすむんだなと思いました。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
未曾有の東日本大震災は莫大な被害を及ぼし、知り合いの大学の先生も被災し、復旧活動とともに、年度末であったことから入学試験、就職、卒業式、学生の安否確認、大学施設の管理、授業再開に向けての対応をされている。もちろんこれだけではないので、空を見て天気を気にする余裕もない時もあるとのこと。
被害者の方々は私の想像を絶する生活をされておられるのである。
このような生活の中でも、私の専門が食の分野であるためか、メールで食生活について時々触れられている。「知り合いの方からいただいた綜合ビタミン剤を飲みました」「温かい蕎麦を振る舞ってもらいました」「カップ麺のつゆを処理する方法を考えました」などを見るにつけて、私で支援できることはないかといつも思う。
多くの人も同様に何か手伝いたいという思いで行動を起こしておられることであろう。しかし、現地に行って被災者の方々を支援するとなると「思い」からのスタートはするのであるが「思い」だけでは困難に遭遇することも多々あるのではないだろうか。
日本調理科学会では、災害救援の他に、大量調理システムの研究開発及び普及促進、地域防災力向上、ネットワーク県境細微などを活動事業としているNPOと一緒に「災害時の炊き出しメニュープロジェクト」を2005年に立ち上げ、「災害時 炊き出しマニュアル」の発行を毎年行ってきている。
このNPOは2004年の中越地震の炊き出しから始まり、能登半島地震、新潟中越沖地震の災害に出動したという経験をもつ団体である。
2008年の岩手・宮城内陸地震では、外部ボランティアの募集がなかったため、出動ができなかったそうである。
メニュー作成にあたってはNPOの出動経験と学会が蓄積している専門知識とで、心理面、調理面、衛生面、栄養面、地方の特色を活かした料理、アレルギー除去食、高齢者用軟食への対応、冷凍食材の利用、食の安全などと毎年テーマを決めて取り組み、朝昼夕の2食・2週間分のメニューをそれぞれの支部で作成した。1食について下準備・調理作業時間を2時間以内に収まるようにし、タイムチャートも合わせて作成している。
メニューだけでなく、炊き出しにあたっての使用機材、炊き出し場所、水、排水、電気、ゴミ処理、食材、食器、現地までの道路状況、駐車・宿泊場所など、すべてマニュアル化されている。このような経験と知識の積み重ねがあってこそ、被災者の方への有効な支援が可能になってくる。このNPOからは、マニュアルの成果を踏まえ、3月19日から活動を継続しておられるとの連絡が入ってきている。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

今日の新聞ピックアップ☆日本に恩返しする外国人
2011年04月17日
海外での報道については、
ニュースで色々な伝え方をされていることがわかります。
今回の記事では、
リーマン・ショックの時に
日本から支援してもらった恩返しをしたいと、
ブラジル人の方たちが集まったということが記事になっています。
海外での報道の仕方をみても、
日本も捨てたもんじゃないな!と
再認識できたのではないでしょうか?
日本人である私自身、
これだから日本は…と思うこともありました。
でも、この記事やニュースを見て、
なんだか日本人であることが誇らしくなったのです。
日本に住むわたしたち日本人が、
もっとよりよく、元気にのびのびと暮らせるように
がんばっていかなければ!と思いました。
みなさんはどう思いましたか?
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
リーマン・ショックで支援受け「日本に恩返し」
東日本大震災の被災地で炊き出しをするため、在日ブラジル人18人が15日夜、美濃加茂市を出発した。約1,000食分の食材を用意し、2日間にわたり宮城県気仙沼市の避難所で、日本人の口に合うように味付けしたステーキ丼を振る舞う。
参加者は「日本に恩返しがしたい」と話している。
美濃加茂市は人口の約1割を外国人が占め、中でもブラジル人が最も多い。愛知県一宮市で多文化共生の活動に取り組んでいるNPO法人「交流ネット」が中心となり、メールなどで参加を呼び掛けたところ、美濃加茂市などからブラジル人らが集まった。
米800キロ、水2,000リットル、牛肉350キロ、ブラジルの菓子などを用意。同市加茂川町の多文化交流センターに集まり、段ボール詰めした食材を車3台に積み込み、現地に向かった。
同法人の船津謙一副理事長(38)は「リーマン・ショックの時は、日本から支援してもらった。今後はお返しがしたい」と語った。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

ニュースで色々な伝え方をされていることがわかります。
今回の記事では、
リーマン・ショックの時に
日本から支援してもらった恩返しをしたいと、
ブラジル人の方たちが集まったということが記事になっています。
海外での報道の仕方をみても、
日本も捨てたもんじゃないな!と
再認識できたのではないでしょうか?
日本人である私自身、
これだから日本は…と思うこともありました。
でも、この記事やニュースを見て、
なんだか日本人であることが誇らしくなったのです。
日本に住むわたしたち日本人が、
もっとよりよく、元気にのびのびと暮らせるように
がんばっていかなければ!と思いました。
みなさんはどう思いましたか?
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
リーマン・ショックで支援受け「日本に恩返し」
東日本大震災の被災地で炊き出しをするため、在日ブラジル人18人が15日夜、美濃加茂市を出発した。約1,000食分の食材を用意し、2日間にわたり宮城県気仙沼市の避難所で、日本人の口に合うように味付けしたステーキ丼を振る舞う。
参加者は「日本に恩返しがしたい」と話している。
美濃加茂市は人口の約1割を外国人が占め、中でもブラジル人が最も多い。愛知県一宮市で多文化共生の活動に取り組んでいるNPO法人「交流ネット」が中心となり、メールなどで参加を呼び掛けたところ、美濃加茂市などからブラジル人らが集まった。
米800キロ、水2,000リットル、牛肉350キロ、ブラジルの菓子などを用意。同市加茂川町の多文化交流センターに集まり、段ボール詰めした食材を車3台に積み込み、現地に向かった。
同法人の船津謙一副理事長(38)は「リーマン・ショックの時は、日本から支援してもらった。今後はお返しがしたい」と語った。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

今日の新聞ピックアップ☆遺児の支援「あしなが育英会」
2011年04月17日
みなさんは「あしなが育英会」をご存知ですか?
病気や災害、自死(自殺)などで親を亡くした子どもたちや、
親が重度後遺障害で働けない家庭の子どもたちを
物心両面で支える民間非営利団体です。(HPより抜粋)
遺児たちへの奨学金などの経済的支援
教育と心のケア
をしている団体です。
阪神・淡路大震災の時には、
遺児(親を亡くした子ども)のための
「神戸レインボーハウス」を設立しています。
その団体の活動の記事が載っていたので、
ご紹介したいと思います。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
震災遺児支援呼び掛け
あしなが事務局 岐阜市で街頭募金
東日本大震災で遺児となった子どもたちを支援する「あしなが学生募金事務局」主催の街頭募金が16日、全国約200カ所で一斉に始まった。県内では、岐阜市神田町の名鉄岐阜駅周辺で行われ、市民から多くの善意が寄せられた。
同局は、病気や事故などで親を亡くし、あしなが育英会から奨学金を受けて学校に通う学生らで構成。
募金活動が毎年2回実施してるが、今回集まった募金は同育英会に全額寄付し、地震・津波遺児に支給する特別一時金や、遺児の心のケアを行う施設の設立資金として活用する。
あしなが学生募金事務局によると、11日現在、東日本大震災により遺児となった252人の児童・生徒から特別一時金の申込みがあったという。
この日は、高校生や大学生のボランティアら約20人が参加。市民らにチラシを配りながら、遺児への支援を訴えた。募金活動に参加した金城学院大3年の堀井千裕さん(21)は「被災地の子どもたちのために少しでも力になれば」と話していた。
活動は17、23、24日にも同駅周辺で行われる。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

病気や災害、自死(自殺)などで親を亡くした子どもたちや、
親が重度後遺障害で働けない家庭の子どもたちを
物心両面で支える民間非営利団体です。(HPより抜粋)
遺児たちへの奨学金などの経済的支援
教育と心のケア
をしている団体です。
阪神・淡路大震災の時には、
遺児(親を亡くした子ども)のための
「神戸レインボーハウス」を設立しています。
その団体の活動の記事が載っていたので、
ご紹介したいと思います。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
震災遺児支援呼び掛け
あしなが事務局 岐阜市で街頭募金
東日本大震災で遺児となった子どもたちを支援する「あしなが学生募金事務局」主催の街頭募金が16日、全国約200カ所で一斉に始まった。県内では、岐阜市神田町の名鉄岐阜駅周辺で行われ、市民から多くの善意が寄せられた。
同局は、病気や事故などで親を亡くし、あしなが育英会から奨学金を受けて学校に通う学生らで構成。
募金活動が毎年2回実施してるが、今回集まった募金は同育英会に全額寄付し、地震・津波遺児に支給する特別一時金や、遺児の心のケアを行う施設の設立資金として活用する。
あしなが学生募金事務局によると、11日現在、東日本大震災により遺児となった252人の児童・生徒から特別一時金の申込みがあったという。
この日は、高校生や大学生のボランティアら約20人が参加。市民らにチラシを配りながら、遺児への支援を訴えた。募金活動に参加した金城学院大3年の堀井千裕さん(21)は「被災地の子どもたちのために少しでも力になれば」と話していた。
活動は17、23、24日にも同駅周辺で行われる。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

今日の新聞ピックアップ☆小学生が発行する「ファイト新聞」
2011年04月17日
宮城県気仙沼市の小学生の呼びかけから、
「ファイト新聞」なるものが作られており、
今回30号が発行されたそうです。
このことが4月に新聞に掲載されたところ、
応援の手紙や、
インスタントカメラが届いたそう。
地震に関してはあまり話したがらないとのことですが、
子どもの前向きさや笑顔が、
まわりの大人を元気づけていることは
確かだと思います。
子どもたちの体験した、目で見た今回の大震災での
心の傷は深く、消えることもないでしょう。
でも、少しずつでも癒されていけばいいなと思います。
こどもたちの笑顔や元気な姿が、
大人に元気やがんばる力を与えてくれること。
これは、飛騨に住むママたちの日々の生活の中でも、
同じように感じることがあるんじゃないかなと思いました。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
“7歳編集長”に反響
避難所の「ファイト新聞」30号発行
宮城県気仙沼市の気仙沼小学校に設けられた東日本大震災の避難所で小学生の呼び掛けによって始まった壁新聞「ファイト新聞」が大きな反響を呼んでいる。取材が相次ぎ、初代編集長の南気仙沼小学校2年吉田里紗ちゃん(7)には応援の手紙も寄せられた。発行は毎日続き、16日で30号目を迎えた。
ファイト新聞は里紗ちゃんの「寂しい避難所を、少しでも明るくしたい」との思いから始まった。「天気がはれだと元気がでます」「ひさびさに食べた日本のカレーはおいしかったです」子どもの目線で見た避難所での生活や感想を色とりどりのペンを使ってB4判の紙につづる。執筆陣は小中学生ら数人が中心になっている。
新聞のことが4月に入って報じられてから、これまでに手紙2通や取材に使ってもらおうとの意図からインスタントカメラ2台も届いた。茨城県の女性は「(里紗ちゃんと)同じ年の子がいるのでとても感動した」と書いた。縦70センチ、横50センチの白い紙に「ゲゲゲの鬼太郎」のイラストとともに「里紗編集長 がんばれ」と書いた応援メッセージを寄せた人もいる。
里紗ちゃんは報道後、間もなく、両親とともに気仙沼市内の祖父方に移ったが、今も2〜3日に1回は避難所に来て新聞制作を手伝う。
妹思いで、友だちとも元気に遊ぶ女の子だが、取材でファイト新聞のことを尋ねると口を閉ざす。母の智子さん(43)は「思わぬ反響を呼んで戸惑っているのかもしれません」と推し量った。小学校で地震に遭ったが、それについてはあまり話したがらない。
里紗ちゃんが避難所を出たため、現在の編集長は気仙沼小学校4年小山里子ちゃん(9)。震災1ヶ月の4月11日の新聞ではピンク色のペンで「この1ヶ月かん いろ×2なことがありました! これからもがんばりましょう」と呼び掛けた。
ファイト新聞について、避難所の西岡春恵さん(47)は「不安な気持ちになることが多い中で、子どもの前向きさが温かかった」と話した。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

「ファイト新聞」なるものが作られており、
今回30号が発行されたそうです。
このことが4月に新聞に掲載されたところ、
応援の手紙や、
インスタントカメラが届いたそう。
地震に関してはあまり話したがらないとのことですが、
子どもの前向きさや笑顔が、
まわりの大人を元気づけていることは
確かだと思います。
子どもたちの体験した、目で見た今回の大震災での
心の傷は深く、消えることもないでしょう。
でも、少しずつでも癒されていけばいいなと思います。
こどもたちの笑顔や元気な姿が、
大人に元気やがんばる力を与えてくれること。
これは、飛騨に住むママたちの日々の生活の中でも、
同じように感じることがあるんじゃないかなと思いました。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
“7歳編集長”に反響
避難所の「ファイト新聞」30号発行
宮城県気仙沼市の気仙沼小学校に設けられた東日本大震災の避難所で小学生の呼び掛けによって始まった壁新聞「ファイト新聞」が大きな反響を呼んでいる。取材が相次ぎ、初代編集長の南気仙沼小学校2年吉田里紗ちゃん(7)には応援の手紙も寄せられた。発行は毎日続き、16日で30号目を迎えた。
ファイト新聞は里紗ちゃんの「寂しい避難所を、少しでも明るくしたい」との思いから始まった。「天気がはれだと元気がでます」「ひさびさに食べた日本のカレーはおいしかったです」子どもの目線で見た避難所での生活や感想を色とりどりのペンを使ってB4判の紙につづる。執筆陣は小中学生ら数人が中心になっている。
新聞のことが4月に入って報じられてから、これまでに手紙2通や取材に使ってもらおうとの意図からインスタントカメラ2台も届いた。茨城県の女性は「(里紗ちゃんと)同じ年の子がいるのでとても感動した」と書いた。縦70センチ、横50センチの白い紙に「ゲゲゲの鬼太郎」のイラストとともに「里紗編集長 がんばれ」と書いた応援メッセージを寄せた人もいる。
里紗ちゃんは報道後、間もなく、両親とともに気仙沼市内の祖父方に移ったが、今も2〜3日に1回は避難所に来て新聞制作を手伝う。
妹思いで、友だちとも元気に遊ぶ女の子だが、取材でファイト新聞のことを尋ねると口を閉ざす。母の智子さん(43)は「思わぬ反響を呼んで戸惑っているのかもしれません」と推し量った。小学校で地震に遭ったが、それについてはあまり話したがらない。
里紗ちゃんが避難所を出たため、現在の編集長は気仙沼小学校4年小山里子ちゃん(9)。震災1ヶ月の4月11日の新聞ではピンク色のペンで「この1ヶ月かん いろ×2なことがありました! これからもがんばりましょう」と呼び掛けた。
ファイト新聞について、避難所の西岡春恵さん(47)は「不安な気持ちになることが多い中で、子どもの前向きさが温かかった」と話した。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

今日の新聞ピックアップ☆がれき処理に3,000億円!!
2011年04月17日
岩手県内でのがれき処理にかかる費用は、
約3,110億円なのだそうです!
金額がデカ過ぎて、想像しきれませんが、
年間の処理量の12年分ということなので、
もう想像を絶する相当な量のがれきを
処理しなければいけないです。
がれきの保管所に必要なスペースは…
なんと東京ドームの約66個分!
津波は住み慣れた家も、
仕事場も、学校も、保育園や幼稚園も、役所も、
すべてをがれきと化してしまったのですね。。。
自分たちの住んでいる家や町が
そんな事態に陥ったら。。。
想像しただけでも恐ろしいです。
もし自分の家が「がれき」と呼ばれるような姿になってしまったら…
言葉に表しようがないくらい悲しく、唖然としてしまうでしょう。
それが現実としてある被災地や被災者の方々…
どんな心境なのでしょうか。。。
察しきれません。。。
でも想い出は消えない。
その想い出を糧に、復興してほしいと思います。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
岩手県の達増拓也知事は16日、県庁で松本龍防災担当相と会談し、東日本大震災により県内で生じたがれきが年間処理量の12年分の約580万トンに上り、処理費用として約3110億円が見込まれると明らかにした。
県は当初380万トンとしていた。増加分は倒壊した建物の確認作業が進んだため。
達増知事は、がれきの保管場所として東京ドーム約66個分に当たる3平方キロメートルの確保が課題とも指摘し、がれき処理などへの国の支援を求めつ要望書を防災担当相に手渡した。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

約3,110億円なのだそうです!
金額がデカ過ぎて、想像しきれませんが、
年間の処理量の12年分ということなので、
もう想像を絶する相当な量のがれきを
処理しなければいけないです。
がれきの保管所に必要なスペースは…
なんと東京ドームの約66個分!
津波は住み慣れた家も、
仕事場も、学校も、保育園や幼稚園も、役所も、
すべてをがれきと化してしまったのですね。。。
自分たちの住んでいる家や町が
そんな事態に陥ったら。。。
想像しただけでも恐ろしいです。
もし自分の家が「がれき」と呼ばれるような姿になってしまったら…
言葉に表しようがないくらい悲しく、唖然としてしまうでしょう。
それが現実としてある被災地や被災者の方々…
どんな心境なのでしょうか。。。
察しきれません。。。
でも想い出は消えない。
その想い出を糧に、復興してほしいと思います。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
岩手県の達増拓也知事は16日、県庁で松本龍防災担当相と会談し、東日本大震災により県内で生じたがれきが年間処理量の12年分の約580万トンに上り、処理費用として約3110億円が見込まれると明らかにした。
県は当初380万トンとしていた。増加分は倒壊した建物の確認作業が進んだため。
達増知事は、がれきの保管場所として東京ドーム約66個分に当たる3平方キロメートルの確保が課題とも指摘し、がれき処理などへの国の支援を求めつ要望書を防災担当相に手渡した。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

Posted by Sparking Holiday 723. at
00:00
│Comments(0)
3.11より1ヶ月がたちました
2011年04月11日
2011年3月11日
14時46分18秒
東日本を襲った大震災。
黙祷をささげるとともに、
今後わたしたちにできることとは何か。
今一度考えて、
カタチにしていきたいと思います。
ご冥福と、今後の復興を
こころよりお祈り致します。
地元飛騨でも、様々な影響が出てきています。
今、経済的な2次災害も話題になっています。
このプロジェクトをはじめる時にお伝えしたとおり、
私たち自身の日々の暮らしを維持することでも、
どこかで役に立っていると私は思います。
無理をせず、できる範囲でご協力いただくことこそ、
「今、わたしたちにできること」なのだと思っています!
1ヶ月がたった今でも、
現地では捜索が続いていたり、
今も離ればなれの家族がいたり、
親を亡くした孤児がいたり、
自分たちの力で復興するんだと頑張る現地の方々がいたり、
現地へ出向いて直接支援をするボランティアや個人がいたり、
すこしずつ前に進んでいる一方、
問題はまだまだ山積みです。
この震災で学んだことを、
私たちは活かしていかなければならないのだと思います。
そういう面からも、
「私たちの身に震災が襲ってきた場合、どこに避難すればいいのか?」
「どんな準備が必要なのか」
「対策は万全なのか?」
といった情報を得ることも大切なんじゃないかと思っています。
そいういった情報も含め、
今回の震災でのこれまでの動きや、
今後の動きをお伝えしていくために、
ブログを設置しました!
報告以外にも、
ママ友のチカラ募金に参加してくださったみなさんとの
情報交換や意見収集など
「参加の場」としても活用していきたいと思います!
ぜひコメントをお寄せください!
まずはブログ立ち上げのご報告まで。
ママ友のチカラ募金 STAFFより
14時46分18秒
東日本を襲った大震災。
黙祷をささげるとともに、
今後わたしたちにできることとは何か。
今一度考えて、
カタチにしていきたいと思います。
ご冥福と、今後の復興を
こころよりお祈り致します。
地元飛騨でも、様々な影響が出てきています。
今、経済的な2次災害も話題になっています。
このプロジェクトをはじめる時にお伝えしたとおり、
私たち自身の日々の暮らしを維持することでも、
どこかで役に立っていると私は思います。
無理をせず、できる範囲でご協力いただくことこそ、
「今、わたしたちにできること」なのだと思っています!
1ヶ月がたった今でも、
現地では捜索が続いていたり、
今も離ればなれの家族がいたり、
親を亡くした孤児がいたり、
自分たちの力で復興するんだと頑張る現地の方々がいたり、
現地へ出向いて直接支援をするボランティアや個人がいたり、
すこしずつ前に進んでいる一方、
問題はまだまだ山積みです。
この震災で学んだことを、
私たちは活かしていかなければならないのだと思います。
そういう面からも、
「私たちの身に震災が襲ってきた場合、どこに避難すればいいのか?」
「どんな準備が必要なのか」
「対策は万全なのか?」
といった情報を得ることも大切なんじゃないかと思っています。
そいういった情報も含め、
今回の震災でのこれまでの動きや、
今後の動きをお伝えしていくために、
ブログを設置しました!
報告以外にも、
ママ友のチカラ募金に参加してくださったみなさんとの
情報交換や意見収集など
「参加の場」としても活用していきたいと思います!
ぜひコメントをお寄せください!
まずはブログ立ち上げのご報告まで。
ママ友のチカラ募金 STAFFより
Posted by Sparking Holiday 723. at
14:46
│Comments(0)