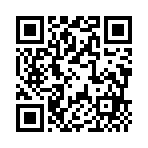スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
今日の新聞ピックアップ☆義援金送金まだ3割
2011年06月06日
みなさんはどこに募金しましたか?
ママ友のチカラ募金に参加してくださった方々の中にも、
日赤や、中央共同募金(通称:赤い羽共同募金)にも
募金した方もいらっしゃると思います。
わたしも日赤にも募金した、その1人です。
新聞やニュースで話題になっているので、
すでにご存知の方も多いとは思いますが、
一応記事を掲載しておきます。
ニュースZEROの中で、
なぜなのか?を調査していました。
被災地は、市役所などの行政機関も被災した地域も多く、
職員も被災したため、人数が不足。
さらに、全体の把握も難しいという状況で、
6月に入ってやっと申請が可能になった地域もあるそう。
全壊や半壊で受け取れる額が異なりますが、
その調査にも、すみずみまで見る必要があるため、
1件あたり約1時間半かかるとのこと。
人材不足に加え、被害範囲もとても広範囲で、
把握するだけでも時間がかかってしまうのが現状のよう。
そうして日々作業に追われている方々の中には、
自身が被災者という方も多いのではないでしょうか。
そんな心境を考えると、
いたたまれません。
募金した側としては、
一刻も早く被災者の元に届けてほしいところですし、
国から人材を大量に派遣すれば、
少しでもスムーズにいく気がしますが、
そう簡単にはいかないようです。
まだ実際に届いていないのは歯がゆいですが、
今後のゆくえも見守っていきたいですね。
だって、気持ちがこもったお金なのだから。
こうして現状を知って思うのは、
「日赤や中央共同募金会への義援金=復興までの長い道のりを生き抜くためのお金」
と考えてもいいのかも知れません。
復興と一言で言っても、
とてつもなく大変なこと。
長い長い道のりです。
そういうカタチであっても
協力できるのならば、
込めた気持ちに無駄はなかったと言えるのでは?
募金したわたしたちも、
募金したから終わり!ではなく、
今後の行方にもしっかり
注目していかなくてはいけませんね。
日赤や中央共同募金以外にも、
さまざまな義援金募集があり、
最終的にどこに行っているのかも異なります。
こんなサイトを発見したので、気になる方は見てみてください。
●募金情報まとめ
http://sites.google.com/site/quake20110311jp/bokin
(モバゲー、GREE、Amazon、Google、楽天 などなど、色々載っています )
ご参考までに。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
義援金送金まだ3割
残高1691億円
日赤、中央共同募金会
被害規模を過大想定
東日本大震災で日赤と中央共同募金会に寄せられた義援金2513億円(6月2日現在)のうち、被災した15都道府県に送金されたのは約3割の822億円にとどまり、残る1691億円は2団体の元にあることが5日、日赤などへの取材で分かった。
被害が広範囲にわたり全体像がつかめない中、日赤や15都道府県などでつくる義援金配分割合決定委員会(事務局・厚生労働省)が4月に被害ごとの金額の基準を決めた際に想定した被害規模が結果的に過大だったことが主原因。委員会は6日の会合で、追加の支給基準を策定し、残金の配分を急ぐ。
委員会は、4月8日に初会合を開催。この時点で義援金は約1300億円あり、少なくとも2100億円に達すると見積もった。後になって義援金が不足する事態を避けるため、犠牲者や損壊家屋などの数は最大規模で想定。把握が難しい家屋の損壊状況は航空写真を参考にした。
こうした想定を基に支給基準は(1)死者・行方不明者1人当たり35万円 (2)家屋全壊35万円、半壊18万円 (3) 福島第1原発から半径30km圏内の世帯に35万円と決まった。
各都道府県は把握できた損害分の送金を要請。被害の大きい東北3県のうち、岩手に101億円、宮城に331億円、福島に350億円が送金された。
被害の把握は進んでいるが、4月の基準に基づく今後の必要額について3県は取材に「あと数億円」(岩手)、「150億円程度」(宮城)、「最大でも70億円」(福島)と回答。他の都道府県を含めても、義援金は大幅に残ることが確実だ。
一方、厚労省によると、15都道府県に送金された822億円のうち被災者に支給された義援金は2日現在287億円にとどまり、支給の遅れが問題になっている。
4月の被害想定の詳細は明らかにされていないが、日赤は「結果的に想定が大きすぎたかもしれないが4月時点では被害の規模が見通せず、やむを得なかった。追加基準が決まれば、要請を受け次第速やかに送金したい」としている。
(2011年6月6日(月)岐阜新聞より)

ママ友のチカラ募金に参加してくださった方々の中にも、
日赤や、中央共同募金(通称:赤い羽共同募金)にも
募金した方もいらっしゃると思います。
わたしも日赤にも募金した、その1人です。
新聞やニュースで話題になっているので、
すでにご存知の方も多いとは思いますが、
一応記事を掲載しておきます。
ニュースZEROの中で、
なぜなのか?を調査していました。
被災地は、市役所などの行政機関も被災した地域も多く、
職員も被災したため、人数が不足。
さらに、全体の把握も難しいという状況で、
6月に入ってやっと申請が可能になった地域もあるそう。
全壊や半壊で受け取れる額が異なりますが、
その調査にも、すみずみまで見る必要があるため、
1件あたり約1時間半かかるとのこと。
人材不足に加え、被害範囲もとても広範囲で、
把握するだけでも時間がかかってしまうのが現状のよう。
そうして日々作業に追われている方々の中には、
自身が被災者という方も多いのではないでしょうか。
そんな心境を考えると、
いたたまれません。
募金した側としては、
一刻も早く被災者の元に届けてほしいところですし、
国から人材を大量に派遣すれば、
少しでもスムーズにいく気がしますが、
そう簡単にはいかないようです。
まだ実際に届いていないのは歯がゆいですが、
今後のゆくえも見守っていきたいですね。
だって、気持ちがこもったお金なのだから。
こうして現状を知って思うのは、
「日赤や中央共同募金会への義援金=復興までの長い道のりを生き抜くためのお金」
と考えてもいいのかも知れません。
復興と一言で言っても、
とてつもなく大変なこと。
長い長い道のりです。
そういうカタチであっても
協力できるのならば、
込めた気持ちに無駄はなかったと言えるのでは?
募金したわたしたちも、
募金したから終わり!ではなく、
今後の行方にもしっかり
注目していかなくてはいけませんね。
日赤や中央共同募金以外にも、
さまざまな義援金募集があり、
最終的にどこに行っているのかも異なります。
こんなサイトを発見したので、気になる方は見てみてください。
●募金情報まとめ
http://sites.google.com/site/quake20110311jp/bokin
(モバゲー、GREE、Amazon、Google、楽天 などなど、色々載っています )
ご参考までに。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
義援金送金まだ3割
残高1691億円
日赤、中央共同募金会
被害規模を過大想定
東日本大震災で日赤と中央共同募金会に寄せられた義援金2513億円(6月2日現在)のうち、被災した15都道府県に送金されたのは約3割の822億円にとどまり、残る1691億円は2団体の元にあることが5日、日赤などへの取材で分かった。
被害が広範囲にわたり全体像がつかめない中、日赤や15都道府県などでつくる義援金配分割合決定委員会(事務局・厚生労働省)が4月に被害ごとの金額の基準を決めた際に想定した被害規模が結果的に過大だったことが主原因。委員会は6日の会合で、追加の支給基準を策定し、残金の配分を急ぐ。
委員会は、4月8日に初会合を開催。この時点で義援金は約1300億円あり、少なくとも2100億円に達すると見積もった。後になって義援金が不足する事態を避けるため、犠牲者や損壊家屋などの数は最大規模で想定。把握が難しい家屋の損壊状況は航空写真を参考にした。
こうした想定を基に支給基準は(1)死者・行方不明者1人当たり35万円 (2)家屋全壊35万円、半壊18万円 (3) 福島第1原発から半径30km圏内の世帯に35万円と決まった。
各都道府県は把握できた損害分の送金を要請。被害の大きい東北3県のうち、岩手に101億円、宮城に331億円、福島に350億円が送金された。
被害の把握は進んでいるが、4月の基準に基づく今後の必要額について3県は取材に「あと数億円」(岩手)、「150億円程度」(宮城)、「最大でも70億円」(福島)と回答。他の都道府県を含めても、義援金は大幅に残ることが確実だ。
一方、厚労省によると、15都道府県に送金された822億円のうち被災者に支給された義援金は2日現在287億円にとどまり、支給の遅れが問題になっている。
4月の被害想定の詳細は明らかにされていないが、日赤は「結果的に想定が大きすぎたかもしれないが4月時点では被害の規模が見通せず、やむを得なかった。追加基準が決まれば、要請を受け次第速やかに送金したい」としている。
(2011年6月6日(月)岐阜新聞より)

今日の新聞ピックアップ☆全国の学校耐震化
2011年04月17日
今回の東日本大震災を受け、
全国の学校耐震化(400億円)が盛り込まれました。
対象が全国なので、
飛騨も例外ではないということでしょう。
私の母校である古川西小学校も、
安全・安心な学校づくり交付金事業の一環で、
耐震と大規模が行われ、ほぼ完了しました。
※参考資料↓
http://www.city.hida.gifu.jp/gyousei/g_oshirase/2011/0311.../taisin_2011.pdf
みなさんのお子さんが通っている学校の
耐震具合はご存知ですか?
この機会に知っておくことも必要なのではないでしょうか?
ちなみに、上記の参考資料は、
「古川西小学校 耐震」とグーグルで検索したら出てきました。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
政府、民主党は16日、東日本大震災の復旧・復興にむけた2011年度第1次補正予算案に関し、全国の学校耐震化経費400億円を新たに盛り込む方針を固めた。野党に配慮した修正で、早期成立へ協力を促す狙い。18日の民主党と自民、公明両党の政策責任者協議で提示する。
また、与野党双方に慎重論があった政府開発援助(ODA)の1千億円の削減幅も500億円に圧縮。これまで7万戸分としていた被災地の仮設住宅建設費は10万戸分に拡大する。
いずれの修正に関しても国債の追加発行などはせず1兆数千億円で調整していた公共時事業費を削減することで帳尻を合わせる考え。
4兆円規模の全体額は維持する。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

全国の学校耐震化(400億円)が盛り込まれました。
対象が全国なので、
飛騨も例外ではないということでしょう。
私の母校である古川西小学校も、
安全・安心な学校づくり交付金事業の一環で、
耐震と大規模が行われ、ほぼ完了しました。
※参考資料↓
http://www.city.hida.gifu.jp/gyousei/g_oshirase/2011/0311.../taisin_2011.pdf
みなさんのお子さんが通っている学校の
耐震具合はご存知ですか?
この機会に知っておくことも必要なのではないでしょうか?
ちなみに、上記の参考資料は、
「古川西小学校 耐震」とグーグルで検索したら出てきました。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
政府、民主党は16日、東日本大震災の復旧・復興にむけた2011年度第1次補正予算案に関し、全国の学校耐震化経費400億円を新たに盛り込む方針を固めた。野党に配慮した修正で、早期成立へ協力を促す狙い。18日の民主党と自民、公明両党の政策責任者協議で提示する。
また、与野党双方に慎重論があった政府開発援助(ODA)の1千億円の削減幅も500億円に圧縮。これまで7万戸分としていた被災地の仮設住宅建設費は10万戸分に拡大する。
いずれの修正に関しても国債の追加発行などはせず1兆数千億円で調整していた公共時事業費を削減することで帳尻を合わせる考え。
4兆円規模の全体額は維持する。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

今日の新聞ピックアップ☆災害時 炊き出しマニュアル
2011年04月17日
現在、様々なボランティア団体によって、
被災地では炊き出しが行われています。
この「炊き出しマニュアル」というのは、
2004年の中越地震から始まり、
能登半島地震や新潟中越沖地震の時にも出動したそう。
※2008年の岩手・宮城内陸地震では、募集がなかったため出動なし。
私は、そのようなマニュアルがあることを
初めて知りました。
記事によると、
このメニューは「災害時 炊き出し」という名にふさわしく、
様々な面からみてあり、メニュー以外のゴミ処理や場所、排水にいたるまで、
実に細かく想定され、マニュアル化されているそうです。
そうなると…
どんなものなのだろう?
実際にみてみたい!と思い、
マニュアルを検索してみましたが、
見つからず。。。
特定非営利活動法人 キャンパー
http://www.camper.ne.jp/npo/
というところが発行しているらしく、
見てみるけれども見当たらない。。。
「災害時炊き出しマニュアル2009-10企業版」
というものも発行されているみたいだけど、
やっぱり見つからない。。。
日本調理科学会のHPにもない。。。
いったいどこに!?
とりあえず、新潟バージョンを見付けたので
リンクしておきます。
御参考までに。
eiyou-niigata.jp/pdf/saigaijisien_nagaoka.pdf
本当に細かくマニュアル化されています。
子どもの頃に地元の子ども会で行ったキャンプの
「キャンプのしおり」を思い出しました。
こうしてあらかじめマニュアル化しておけば、
いざという時に、ドタバタしなくてすむんだなと思いました。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
未曾有の東日本大震災は莫大な被害を及ぼし、知り合いの大学の先生も被災し、復旧活動とともに、年度末であったことから入学試験、就職、卒業式、学生の安否確認、大学施設の管理、授業再開に向けての対応をされている。もちろんこれだけではないので、空を見て天気を気にする余裕もない時もあるとのこと。
被害者の方々は私の想像を絶する生活をされておられるのである。
このような生活の中でも、私の専門が食の分野であるためか、メールで食生活について時々触れられている。「知り合いの方からいただいた綜合ビタミン剤を飲みました」「温かい蕎麦を振る舞ってもらいました」「カップ麺のつゆを処理する方法を考えました」などを見るにつけて、私で支援できることはないかといつも思う。
多くの人も同様に何か手伝いたいという思いで行動を起こしておられることであろう。しかし、現地に行って被災者の方々を支援するとなると「思い」からのスタートはするのであるが「思い」だけでは困難に遭遇することも多々あるのではないだろうか。
日本調理科学会では、災害救援の他に、大量調理システムの研究開発及び普及促進、地域防災力向上、ネットワーク県境細微などを活動事業としているNPOと一緒に「災害時の炊き出しメニュープロジェクト」を2005年に立ち上げ、「災害時 炊き出しマニュアル」の発行を毎年行ってきている。
このNPOは2004年の中越地震の炊き出しから始まり、能登半島地震、新潟中越沖地震の災害に出動したという経験をもつ団体である。
2008年の岩手・宮城内陸地震では、外部ボランティアの募集がなかったため、出動ができなかったそうである。
メニュー作成にあたってはNPOの出動経験と学会が蓄積している専門知識とで、心理面、調理面、衛生面、栄養面、地方の特色を活かした料理、アレルギー除去食、高齢者用軟食への対応、冷凍食材の利用、食の安全などと毎年テーマを決めて取り組み、朝昼夕の2食・2週間分のメニューをそれぞれの支部で作成した。1食について下準備・調理作業時間を2時間以内に収まるようにし、タイムチャートも合わせて作成している。
メニューだけでなく、炊き出しにあたっての使用機材、炊き出し場所、水、排水、電気、ゴミ処理、食材、食器、現地までの道路状況、駐車・宿泊場所など、すべてマニュアル化されている。このような経験と知識の積み重ねがあってこそ、被災者の方への有効な支援が可能になってくる。このNPOからは、マニュアルの成果を踏まえ、3月19日から活動を継続しておられるとの連絡が入ってきている。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

被災地では炊き出しが行われています。
この「炊き出しマニュアル」というのは、
2004年の中越地震から始まり、
能登半島地震や新潟中越沖地震の時にも出動したそう。
※2008年の岩手・宮城内陸地震では、募集がなかったため出動なし。
私は、そのようなマニュアルがあることを
初めて知りました。
記事によると、
このメニューは「災害時 炊き出し」という名にふさわしく、
様々な面からみてあり、メニュー以外のゴミ処理や場所、排水にいたるまで、
実に細かく想定され、マニュアル化されているそうです。
そうなると…
どんなものなのだろう?
実際にみてみたい!と思い、
マニュアルを検索してみましたが、
見つからず。。。
特定非営利活動法人 キャンパー
http://www.camper.ne.jp/npo/
というところが発行しているらしく、
見てみるけれども見当たらない。。。
「災害時炊き出しマニュアル2009-10企業版」
というものも発行されているみたいだけど、
やっぱり見つからない。。。
日本調理科学会のHPにもない。。。
いったいどこに!?
とりあえず、新潟バージョンを見付けたので
リンクしておきます。
御参考までに。
eiyou-niigata.jp/pdf/saigaijisien_nagaoka.pdf
本当に細かくマニュアル化されています。
子どもの頃に地元の子ども会で行ったキャンプの
「キャンプのしおり」を思い出しました。
こうしてあらかじめマニュアル化しておけば、
いざという時に、ドタバタしなくてすむんだなと思いました。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
未曾有の東日本大震災は莫大な被害を及ぼし、知り合いの大学の先生も被災し、復旧活動とともに、年度末であったことから入学試験、就職、卒業式、学生の安否確認、大学施設の管理、授業再開に向けての対応をされている。もちろんこれだけではないので、空を見て天気を気にする余裕もない時もあるとのこと。
被害者の方々は私の想像を絶する生活をされておられるのである。
このような生活の中でも、私の専門が食の分野であるためか、メールで食生活について時々触れられている。「知り合いの方からいただいた綜合ビタミン剤を飲みました」「温かい蕎麦を振る舞ってもらいました」「カップ麺のつゆを処理する方法を考えました」などを見るにつけて、私で支援できることはないかといつも思う。
多くの人も同様に何か手伝いたいという思いで行動を起こしておられることであろう。しかし、現地に行って被災者の方々を支援するとなると「思い」からのスタートはするのであるが「思い」だけでは困難に遭遇することも多々あるのではないだろうか。
日本調理科学会では、災害救援の他に、大量調理システムの研究開発及び普及促進、地域防災力向上、ネットワーク県境細微などを活動事業としているNPOと一緒に「災害時の炊き出しメニュープロジェクト」を2005年に立ち上げ、「災害時 炊き出しマニュアル」の発行を毎年行ってきている。
このNPOは2004年の中越地震の炊き出しから始まり、能登半島地震、新潟中越沖地震の災害に出動したという経験をもつ団体である。
2008年の岩手・宮城内陸地震では、外部ボランティアの募集がなかったため、出動ができなかったそうである。
メニュー作成にあたってはNPOの出動経験と学会が蓄積している専門知識とで、心理面、調理面、衛生面、栄養面、地方の特色を活かした料理、アレルギー除去食、高齢者用軟食への対応、冷凍食材の利用、食の安全などと毎年テーマを決めて取り組み、朝昼夕の2食・2週間分のメニューをそれぞれの支部で作成した。1食について下準備・調理作業時間を2時間以内に収まるようにし、タイムチャートも合わせて作成している。
メニューだけでなく、炊き出しにあたっての使用機材、炊き出し場所、水、排水、電気、ゴミ処理、食材、食器、現地までの道路状況、駐車・宿泊場所など、すべてマニュアル化されている。このような経験と知識の積み重ねがあってこそ、被災者の方への有効な支援が可能になってくる。このNPOからは、マニュアルの成果を踏まえ、3月19日から活動を継続しておられるとの連絡が入ってきている。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

今日の新聞ピックアップ☆日本に恩返しする外国人
2011年04月17日
海外での報道については、
ニュースで色々な伝え方をされていることがわかります。
今回の記事では、
リーマン・ショックの時に
日本から支援してもらった恩返しをしたいと、
ブラジル人の方たちが集まったということが記事になっています。
海外での報道の仕方をみても、
日本も捨てたもんじゃないな!と
再認識できたのではないでしょうか?
日本人である私自身、
これだから日本は…と思うこともありました。
でも、この記事やニュースを見て、
なんだか日本人であることが誇らしくなったのです。
日本に住むわたしたち日本人が、
もっとよりよく、元気にのびのびと暮らせるように
がんばっていかなければ!と思いました。
みなさんはどう思いましたか?
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
リーマン・ショックで支援受け「日本に恩返し」
東日本大震災の被災地で炊き出しをするため、在日ブラジル人18人が15日夜、美濃加茂市を出発した。約1,000食分の食材を用意し、2日間にわたり宮城県気仙沼市の避難所で、日本人の口に合うように味付けしたステーキ丼を振る舞う。
参加者は「日本に恩返しがしたい」と話している。
美濃加茂市は人口の約1割を外国人が占め、中でもブラジル人が最も多い。愛知県一宮市で多文化共生の活動に取り組んでいるNPO法人「交流ネット」が中心となり、メールなどで参加を呼び掛けたところ、美濃加茂市などからブラジル人らが集まった。
米800キロ、水2,000リットル、牛肉350キロ、ブラジルの菓子などを用意。同市加茂川町の多文化交流センターに集まり、段ボール詰めした食材を車3台に積み込み、現地に向かった。
同法人の船津謙一副理事長(38)は「リーマン・ショックの時は、日本から支援してもらった。今後はお返しがしたい」と語った。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

ニュースで色々な伝え方をされていることがわかります。
今回の記事では、
リーマン・ショックの時に
日本から支援してもらった恩返しをしたいと、
ブラジル人の方たちが集まったということが記事になっています。
海外での報道の仕方をみても、
日本も捨てたもんじゃないな!と
再認識できたのではないでしょうか?
日本人である私自身、
これだから日本は…と思うこともありました。
でも、この記事やニュースを見て、
なんだか日本人であることが誇らしくなったのです。
日本に住むわたしたち日本人が、
もっとよりよく、元気にのびのびと暮らせるように
がんばっていかなければ!と思いました。
みなさんはどう思いましたか?
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
リーマン・ショックで支援受け「日本に恩返し」
東日本大震災の被災地で炊き出しをするため、在日ブラジル人18人が15日夜、美濃加茂市を出発した。約1,000食分の食材を用意し、2日間にわたり宮城県気仙沼市の避難所で、日本人の口に合うように味付けしたステーキ丼を振る舞う。
参加者は「日本に恩返しがしたい」と話している。
美濃加茂市は人口の約1割を外国人が占め、中でもブラジル人が最も多い。愛知県一宮市で多文化共生の活動に取り組んでいるNPO法人「交流ネット」が中心となり、メールなどで参加を呼び掛けたところ、美濃加茂市などからブラジル人らが集まった。
米800キロ、水2,000リットル、牛肉350キロ、ブラジルの菓子などを用意。同市加茂川町の多文化交流センターに集まり、段ボール詰めした食材を車3台に積み込み、現地に向かった。
同法人の船津謙一副理事長(38)は「リーマン・ショックの時は、日本から支援してもらった。今後はお返しがしたい」と語った。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

今日の新聞ピックアップ☆遺児の支援「あしなが育英会」
2011年04月17日
みなさんは「あしなが育英会」をご存知ですか?
病気や災害、自死(自殺)などで親を亡くした子どもたちや、
親が重度後遺障害で働けない家庭の子どもたちを
物心両面で支える民間非営利団体です。(HPより抜粋)
遺児たちへの奨学金などの経済的支援
教育と心のケア
をしている団体です。
阪神・淡路大震災の時には、
遺児(親を亡くした子ども)のための
「神戸レインボーハウス」を設立しています。
その団体の活動の記事が載っていたので、
ご紹介したいと思います。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
震災遺児支援呼び掛け
あしなが事務局 岐阜市で街頭募金
東日本大震災で遺児となった子どもたちを支援する「あしなが学生募金事務局」主催の街頭募金が16日、全国約200カ所で一斉に始まった。県内では、岐阜市神田町の名鉄岐阜駅周辺で行われ、市民から多くの善意が寄せられた。
同局は、病気や事故などで親を亡くし、あしなが育英会から奨学金を受けて学校に通う学生らで構成。
募金活動が毎年2回実施してるが、今回集まった募金は同育英会に全額寄付し、地震・津波遺児に支給する特別一時金や、遺児の心のケアを行う施設の設立資金として活用する。
あしなが学生募金事務局によると、11日現在、東日本大震災により遺児となった252人の児童・生徒から特別一時金の申込みがあったという。
この日は、高校生や大学生のボランティアら約20人が参加。市民らにチラシを配りながら、遺児への支援を訴えた。募金活動に参加した金城学院大3年の堀井千裕さん(21)は「被災地の子どもたちのために少しでも力になれば」と話していた。
活動は17、23、24日にも同駅周辺で行われる。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

病気や災害、自死(自殺)などで親を亡くした子どもたちや、
親が重度後遺障害で働けない家庭の子どもたちを
物心両面で支える民間非営利団体です。(HPより抜粋)
遺児たちへの奨学金などの経済的支援
教育と心のケア
をしている団体です。
阪神・淡路大震災の時には、
遺児(親を亡くした子ども)のための
「神戸レインボーハウス」を設立しています。
その団体の活動の記事が載っていたので、
ご紹介したいと思います。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
震災遺児支援呼び掛け
あしなが事務局 岐阜市で街頭募金
東日本大震災で遺児となった子どもたちを支援する「あしなが学生募金事務局」主催の街頭募金が16日、全国約200カ所で一斉に始まった。県内では、岐阜市神田町の名鉄岐阜駅周辺で行われ、市民から多くの善意が寄せられた。
同局は、病気や事故などで親を亡くし、あしなが育英会から奨学金を受けて学校に通う学生らで構成。
募金活動が毎年2回実施してるが、今回集まった募金は同育英会に全額寄付し、地震・津波遺児に支給する特別一時金や、遺児の心のケアを行う施設の設立資金として活用する。
あしなが学生募金事務局によると、11日現在、東日本大震災により遺児となった252人の児童・生徒から特別一時金の申込みがあったという。
この日は、高校生や大学生のボランティアら約20人が参加。市民らにチラシを配りながら、遺児への支援を訴えた。募金活動に参加した金城学院大3年の堀井千裕さん(21)は「被災地の子どもたちのために少しでも力になれば」と話していた。
活動は17、23、24日にも同駅周辺で行われる。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

今日の新聞ピックアップ☆小学生が発行する「ファイト新聞」
2011年04月17日
宮城県気仙沼市の小学生の呼びかけから、
「ファイト新聞」なるものが作られており、
今回30号が発行されたそうです。
このことが4月に新聞に掲載されたところ、
応援の手紙や、
インスタントカメラが届いたそう。
地震に関してはあまり話したがらないとのことですが、
子どもの前向きさや笑顔が、
まわりの大人を元気づけていることは
確かだと思います。
子どもたちの体験した、目で見た今回の大震災での
心の傷は深く、消えることもないでしょう。
でも、少しずつでも癒されていけばいいなと思います。
こどもたちの笑顔や元気な姿が、
大人に元気やがんばる力を与えてくれること。
これは、飛騨に住むママたちの日々の生活の中でも、
同じように感じることがあるんじゃないかなと思いました。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
“7歳編集長”に反響
避難所の「ファイト新聞」30号発行
宮城県気仙沼市の気仙沼小学校に設けられた東日本大震災の避難所で小学生の呼び掛けによって始まった壁新聞「ファイト新聞」が大きな反響を呼んでいる。取材が相次ぎ、初代編集長の南気仙沼小学校2年吉田里紗ちゃん(7)には応援の手紙も寄せられた。発行は毎日続き、16日で30号目を迎えた。
ファイト新聞は里紗ちゃんの「寂しい避難所を、少しでも明るくしたい」との思いから始まった。「天気がはれだと元気がでます」「ひさびさに食べた日本のカレーはおいしかったです」子どもの目線で見た避難所での生活や感想を色とりどりのペンを使ってB4判の紙につづる。執筆陣は小中学生ら数人が中心になっている。
新聞のことが4月に入って報じられてから、これまでに手紙2通や取材に使ってもらおうとの意図からインスタントカメラ2台も届いた。茨城県の女性は「(里紗ちゃんと)同じ年の子がいるのでとても感動した」と書いた。縦70センチ、横50センチの白い紙に「ゲゲゲの鬼太郎」のイラストとともに「里紗編集長 がんばれ」と書いた応援メッセージを寄せた人もいる。
里紗ちゃんは報道後、間もなく、両親とともに気仙沼市内の祖父方に移ったが、今も2〜3日に1回は避難所に来て新聞制作を手伝う。
妹思いで、友だちとも元気に遊ぶ女の子だが、取材でファイト新聞のことを尋ねると口を閉ざす。母の智子さん(43)は「思わぬ反響を呼んで戸惑っているのかもしれません」と推し量った。小学校で地震に遭ったが、それについてはあまり話したがらない。
里紗ちゃんが避難所を出たため、現在の編集長は気仙沼小学校4年小山里子ちゃん(9)。震災1ヶ月の4月11日の新聞ではピンク色のペンで「この1ヶ月かん いろ×2なことがありました! これからもがんばりましょう」と呼び掛けた。
ファイト新聞について、避難所の西岡春恵さん(47)は「不安な気持ちになることが多い中で、子どもの前向きさが温かかった」と話した。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)

「ファイト新聞」なるものが作られており、
今回30号が発行されたそうです。
このことが4月に新聞に掲載されたところ、
応援の手紙や、
インスタントカメラが届いたそう。
地震に関してはあまり話したがらないとのことですが、
子どもの前向きさや笑顔が、
まわりの大人を元気づけていることは
確かだと思います。
子どもたちの体験した、目で見た今回の大震災での
心の傷は深く、消えることもないでしょう。
でも、少しずつでも癒されていけばいいなと思います。
こどもたちの笑顔や元気な姿が、
大人に元気やがんばる力を与えてくれること。
これは、飛騨に住むママたちの日々の生活の中でも、
同じように感じることがあるんじゃないかなと思いました。
〜ママ友のチカラ募金 STAFFより〜
▼ピックアップ記事全文はこちら。
“7歳編集長”に反響
避難所の「ファイト新聞」30号発行
宮城県気仙沼市の気仙沼小学校に設けられた東日本大震災の避難所で小学生の呼び掛けによって始まった壁新聞「ファイト新聞」が大きな反響を呼んでいる。取材が相次ぎ、初代編集長の南気仙沼小学校2年吉田里紗ちゃん(7)には応援の手紙も寄せられた。発行は毎日続き、16日で30号目を迎えた。
ファイト新聞は里紗ちゃんの「寂しい避難所を、少しでも明るくしたい」との思いから始まった。「天気がはれだと元気がでます」「ひさびさに食べた日本のカレーはおいしかったです」子どもの目線で見た避難所での生活や感想を色とりどりのペンを使ってB4判の紙につづる。執筆陣は小中学生ら数人が中心になっている。
新聞のことが4月に入って報じられてから、これまでに手紙2通や取材に使ってもらおうとの意図からインスタントカメラ2台も届いた。茨城県の女性は「(里紗ちゃんと)同じ年の子がいるのでとても感動した」と書いた。縦70センチ、横50センチの白い紙に「ゲゲゲの鬼太郎」のイラストとともに「里紗編集長 がんばれ」と書いた応援メッセージを寄せた人もいる。
里紗ちゃんは報道後、間もなく、両親とともに気仙沼市内の祖父方に移ったが、今も2〜3日に1回は避難所に来て新聞制作を手伝う。
妹思いで、友だちとも元気に遊ぶ女の子だが、取材でファイト新聞のことを尋ねると口を閉ざす。母の智子さん(43)は「思わぬ反響を呼んで戸惑っているのかもしれません」と推し量った。小学校で地震に遭ったが、それについてはあまり話したがらない。
里紗ちゃんが避難所を出たため、現在の編集長は気仙沼小学校4年小山里子ちゃん(9)。震災1ヶ月の4月11日の新聞ではピンク色のペンで「この1ヶ月かん いろ×2なことがありました! これからもがんばりましょう」と呼び掛けた。
ファイト新聞について、避難所の西岡春恵さん(47)は「不安な気持ちになることが多い中で、子どもの前向きさが温かかった」と話した。
(2011年4月17日(日)岐阜新聞より)